第一テーマ館 田舎で「美しく」暮らす

合理的思考の進んだ現代においては、「信じる」ということが、不当に排斥されてしまっているように思えてなりませ
ん。
ん。
それは、日ごろ目にする様々な宗教団体や圧力団体、あるいは政党なども含めて、なんらかの信条で結束している
団体・組織を外から見た場合、ほとんど疑いや不信の眼差しを意識的、無意識的にもつ日本人があまりに多いことに
も如実にあらわれており、外国のように何らかの信仰をもつことがあたりまえの国々と違って、日本独特の環境である
ともいえます。
団体・組織を外から見た場合、ほとんど疑いや不信の眼差しを意識的、無意識的にもつ日本人があまりに多いことに
も如実にあらわれており、外国のように何らかの信仰をもつことがあたりまえの国々と違って、日本独特の環境である
ともいえます。
かといって私自身も、仏教は大好きであっても、なんら信仰といえるような信条は持ち合わせていないのですが、この
ような現代日本の風土が「信じる」という人間の大切な感情と行為をあまりにも遠ざけてはいないでしょうか。
ような現代日本の風土が「信じる」という人間の大切な感情と行為をあまりにも遠ざけてはいないでしょうか。
「客観性」や「合理性」を隠れ蓑にして、「信じる」勇気を失っているとはいえないでしょうか。
そのことを考えさせてくれる本を、以下3つの観点でご紹介したいと思います。
その第一は、認識上の「わかる」ということと「信じる」ということとの決定的な違いです。
石原慎太郎が『法華経を生きる』のなかで、プラグマティストのウィリアム・ジェイムスの言葉を引用して、次のように
語っています。
語っています。
「つまり、懐疑的な態度は選択の回避ではなく、それも一種の選択である。それは、大事なものを、迷うことで実際に
はすでに取り逃がしてしまった危険な選択なのだ、と彼はいいます。つまり、果敢に信じてみろ、ということですが。
はすでに取り逃がしてしまった危険な選択なのだ、と彼はいいます。つまり、果敢に信じてみろ、ということですが。
信じるということは、よく知るということとは決定的に違います。
知るということはあくまで五感を踏まえて成り立つ常識をもう一つ超えた心の作業です。譬えていえば、誰でも人間は
必ず死ぬと知っているが、そう知ることを、そう信じているといいはしない。人間は死んだ後別の世界へ行くのだ、という
ことは誰も理屈だてて立証できないし、そんな世界があるということの証拠もない。そこへ行ってしばらく滞在しまた戻っ
てきた者などいはしないから、来世があるかないかということはあくまで信じる信じないの問題です。
必ず死ぬと知っているが、そう知ることを、そう信じているといいはしない。人間は死んだ後別の世界へ行くのだ、という
ことは誰も理屈だてて立証できないし、そんな世界があるということの証拠もない。そこへ行ってしばらく滞在しまた戻っ
てきた者などいはしないから、来世があるかないかということはあくまで信じる信じないの問題です。
つまり、信仰は現実を越えた対象を構えての心の作業だから、最後は信じるか否かの問題になる。果敢に信じろ、と
はいうが、実は何かを信じるということそのものがすでに果敢な行為ともいえます。」
はいうが、実は何かを信じるということそのものがすでに果敢な行為ともいえます。」
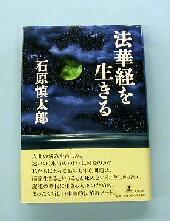
石原慎太郎が法華経について本を出していることも、また、当テーマ館が石原慎太郎を取り上げることも、多くの人からは意外に見えることかも
しれませんが、どちらも、石原慎太郎流に言えば「大きなお世話!」。世間相場の意識を現代人はあまりにも気にしすぎています。
しれませんが、どちらも、石原慎太郎流に言えば「大きなお世話!」。世間相場の意識を現代人はあまりにも気にしすぎています。
もっと自分の信じることを大切にして、果敢に攻めることが今日ほど求められている時代もないのではないでしょうか。
それから、第二の観点は、「人を信じる」ことの大切さのことです。
納税者番付で常に5位以内に位置している著者、銀座日本漢方研究所創設者、斎藤一人さんの言葉は、外国の億
万長者の成功談などよりもはるかに多くのことをいつも説得力をもって教えてくれます。
万長者の成功談などよりもはるかに多くのことをいつも説得力をもって教えてくれます。
斎藤一人さんは「日本のお母さん」ではなく「世界のお母さん」になりなさいという。
「日本のお母さん」とはなにかというと、心配する、謙遜する。
「あんたのことが心配で・・・」「うちの子は駄目で駄目で・・・・・」
それに対して、「世界のお母さん」は「大丈夫だよ、信じているから」という。「お母さん信じているから大丈夫だよ」と。
「心配だ」ということは、どういうことかというと、「信じていない」ということです。
親から「信じていない」といわれる子供がどうして立派になれるでしょう。
まず「信じているよ」といってあげられることが、どれだけ相手の心に自信を与えることか。
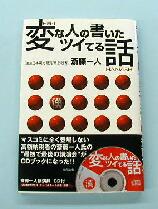
そして、第三の観点は、このテーマ館のブックリストにもその傾向があらわれてしまっているのですが、「信じる」ことや
「信仰」そのものを、常に別の問題に置き換えたり、すりかえたりすることで話してしまい、肝心な宗教(信仰)としての側
面を真正面にすえていないことがあまりにも多いのではないかということです。
「信仰」そのものを、常に別の問題に置き換えたり、すりかえたりすることで話してしまい、肝心な宗教(信仰)としての側
面を真正面にすえていないことがあまりにも多いのではないかということです。
特に私たちが、道元や親鸞などを語るとき、その宗教としての本質を忘れ、あるいは無視して、社会観や人間観で利
用できる側面だけを取り出して良しとしてしまっていることです。
用できる側面だけを取り出して良しとしてしまっていることです。
もちろん、そのような読まれ方も決して否定されるべきものではありませんが、梅原猛は、特に知識人に多いこのよう
な傾向を厳しく戒めています。
な傾向を厳しく戒めています。
「明治以後、日本のインテリに、もっとももてはやされた宗教は、禅と浄土真宗であった。道元と親鸞が、もっとも尊敬された日本の宗教家であっ
たが、私はこの選択も、はなはだ浅薄な理由によっておこなわれたのではないかと思う。なぜなら親鸞が、日本の思想家にもっとも尊敬された理
由は、罪の意識と懺悔の精神にあるようであるが、罪とか懺悔とかはキリスト教的なものではないか。つまり親鸞が、日本のインテリに尊敬された
のは、それがキリスト教の代用品をつとめたことによってではないか。一方禅は合理をこえた超合理の世界として尊ばれる。それはあくまで人間的
な宗教でありながら、単なる西洋の合理主義では到達できない非合理の世界、キリスト教の有に対して無の世界を説くと云われる。こういう合理
に対する非合理、有に対する無という比較の仕方はあまりにも、簡単すぎはしないか。」として、さらに
たが、私はこの選択も、はなはだ浅薄な理由によっておこなわれたのではないかと思う。なぜなら親鸞が、日本の思想家にもっとも尊敬された理
由は、罪の意識と懺悔の精神にあるようであるが、罪とか懺悔とかはキリスト教的なものではないか。つまり親鸞が、日本のインテリに尊敬された
のは、それがキリスト教の代用品をつとめたことによってではないか。一方禅は合理をこえた超合理の世界として尊ばれる。それはあくまで人間的
な宗教でありながら、単なる西洋の合理主義では到達できない非合理の世界、キリスト教の有に対して無の世界を説くと云われる。こういう合理
に対する非合理、有に対する無という比較の仕方はあまりにも、簡単すぎはしないか。」として、さらに
「もう一度、己れの生命の問題を、世界の文化の未来の問題と対決させて考える徹底的な宗教批判が必要なのである。国学や、水戸学のよう
な安価な宗教批判で宗教に別れを告げるとき、人間の魂は、実に浅薄になりはてるのである。われわれも新しい宗教批判の道を用意せねばなら
ぬが、その前に、この痴呆化が、どんなにすぐれた思想家の思想をも不毛にしているかを探らねばならない。」と、徹底抗戦を呼びかけています。
な安価な宗教批判で宗教に別れを告げるとき、人間の魂は、実に浅薄になりはてるのである。われわれも新しい宗教批判の道を用意せねばなら
ぬが、その前に、この痴呆化が、どんなにすぐれた思想家の思想をも不毛にしているかを探らねばならない。」と、徹底抗戦を呼びかけています。
原文では前後しますが、さらにこんなことも付け加えています。
「漢文教育にしても、そうである。そこでは『論語』を読み、『孟子』を読み、『十八史略』を読むが、なぜ『観無量寿経』を、なぜ『法華経』を、特に日
本人にもっとも読まれた仏典である『観音経』を読もうとしないのか。私たちの祖先は、おそらく、『論語』や、『孟子』より、それら仏典の方に親し
み、日本の文化には、それらの仏典の影響が深く及んでいるはずなのに、もう日本人はすっかり、それらの仏典から遠ざかってしまった。」
本人にもっとも読まれた仏典である『観音経』を読もうとしないのか。私たちの祖先は、おそらく、『論語』や、『孟子』より、それら仏典の方に親し
み、日本の文化には、それらの仏典の影響が深く及んでいるはずなのに、もう日本人はすっかり、それらの仏典から遠ざかってしまった。」
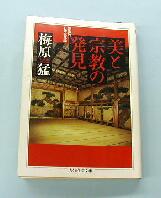
冒頭に述べたように、「信じる勇気」が無いばかりに、私たちは「宗教」を「宗教」としては見ずに、その社会的な効用
や功罪の面からばかり語ってはいないでしょうか。
や功罪の面からばかり語ってはいないでしょうか。
否、否!、これこそ学者の言葉よりも肝心な宗教者のことばを聞かなければなりません。
現代の学者たちは、やれ既成宗教は力がないの、やれ仏教で将来の民心の感化がむずかしいのと論じてなにか一つの、仏教でもなく、儒教で
もなく、耶蘇教でもなく、これらを渾然同化して一新宗教ができねばならぬというておる。かれらは、自分が無信仰であって仏の慈悲によって力を
得ることができぬのであるのを悔いて、信に入って御力を受ければよいのを、それをせんともせずして、自分の無信仰を土台として、やれ既成宗教
がどうだの、やれ従来の仏教がだめだのと申さるることはいかにも片腹痛いしだいでありませんか。
もなく、耶蘇教でもなく、これらを渾然同化して一新宗教ができねばならぬというておる。かれらは、自分が無信仰であって仏の慈悲によって力を
得ることができぬのであるのを悔いて、信に入って御力を受ければよいのを、それをせんともせずして、自分の無信仰を土台として、やれ既成宗教
がどうだの、やれ従来の仏教がだめだのと申さるることはいかにも片腹痛いしだいでありませんか。
かれらは自分の少しばかりの知識をもって道を造りだそうとしておる。蟷螂の斧をもって牛車に向かうとはすなわち現代の学者たちの謂ではない
か。私はこれらの人に、その高慢の角を折って如来がすでに案じいだされた道に帰入することを勧めたい。自分の30年や50年の読書や経験で得
た知識が何になるか、そんな小知見をもって永遠の大道を案じいだそうとはあまりの高慢ではないか。道の指導は道を行く者のすることである。
か。私はこれらの人に、その高慢の角を折って如来がすでに案じいだされた道に帰入することを勧めたい。自分の30年や50年の読書や経験で得
た知識が何になるか、そんな小知見をもって永遠の大道を案じいだそうとはあまりの高慢ではないか。道の指導は道を行く者のすることである。
(暁烏 敏 『歎異抄講和』講談社学術文庫 より)

日本においては「宗教」というものの地位が、諸外国に比べると比較的低い面がありますが、社会意識のなかで「宗
教」の占める位置は、世界中どこの国を見ても、文化の進展度にかかわりなく圧倒的地位をいまだにもっています。
教」の占める位置は、世界中どこの国を見ても、文化の進展度にかかわりなく圧倒的地位をいまだにもっています。
しかし、また裏をかえすようですが、もっと率直な立場から日本的自然崇拝をベースにした日本人の信仰心は、もとも
と「信じる」といった宗教心は強要しないといった見方もあります。
と「信じる」といった宗教心は強要しないといった見方もあります。
それは、西洋の一神教の排他的文化に対して、「和」の文化というより、自然崇拝をベースにした多神教の世界観こ
そ、日本文化をもっとも説明しやすい見方であるといえることです
そ、日本文化をもっとも説明しやすい見方であるといえることです
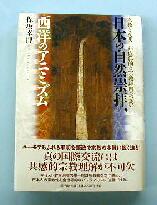
保坂幸博氏の本書は分厚い本にもかかわらず、他のあらゆる宗教入門書や文化人類学の本よりも、読みやすい文
体と表現で、世界における宗教とは何か、日本と西洋との対比をわかりやすく一気に解き明かす内容になっています。
体と表現で、世界における宗教とは何か、日本と西洋との対比をわかりやすく一気に解き明かす内容になっています。
これからの時代は、多神教の文化が世界的に見直されてくることと思います。
そもそも日本人のアイデンティティーとは何かといった疑問に対して、国粋主義におちいるでもなく、人種論におちいる
でもなく、このように切り込んでいる本はなかったかもしれません。
でもなく、このように切り込んでいる本はなかったかもしれません。

さて、ここでもう一度、それでもまだ信じることをためらう圧倒的多数の人びとへ、仏教在家の側からおくる決定的な
言葉を、ここに紹介しましょう。
言葉を、ここに紹介しましょう。
第3回 「仏教を学ぶ心構えについて」より
5、信じてはいけない
さて、仏教に限らず、宗教を学ぶに際して、俗に「鰯の頭も信心」などといって、信ずることを強調し、なんでも頭から
信じ込むことが信仰であるように思い込んでいる人もおられるように思いますが、わたしは、このような態度に反対で
す。考える(疑う)ことを放棄している人と交わると、なんとも異様な感じを受けるものです。人は本来、信じることなど出
来ないものです。信じることが出来ない者が信じるということは、人にも自分にも嘘のポーズをとっているということで
す。これを親鸞は「賢善精進の相をほかにしめして、うちには虚仮をいだけるもの」と言いました。
信じ込むことが信仰であるように思い込んでいる人もおられるように思いますが、わたしは、このような態度に反対で
す。考える(疑う)ことを放棄している人と交わると、なんとも異様な感じを受けるものです。人は本来、信じることなど出
来ないものです。信じることが出来ない者が信じるということは、人にも自分にも嘘のポーズをとっているということで
す。これを親鸞は「賢善精進の相をほかにしめして、うちには虚仮をいだけるもの」と言いました。
宗教とは、最終的に、精神的な大転換(親鸞の言う「横超断四流」信心獲得)を経験しなければ、その真髄を理解す
ることはできないことも事実ではありますが、そのプロセスにおいては、常識的な感覚、知的な理解を大切にして、変な
信仰に固まらない、狂信、強信の人たちに近づかないことが大切です。ときに、迷い疲れて、なにかを信じたいと思う気
持ちになることがありますが、結局は、迷いの上塗りに終わるものです。
ることはできないことも事実ではありますが、そのプロセスにおいては、常識的な感覚、知的な理解を大切にして、変な
信仰に固まらない、狂信、強信の人たちに近づかないことが大切です。ときに、迷い疲れて、なにかを信じたいと思う気
持ちになることがありますが、結局は、迷いの上塗りに終わるものです。
具体的に言えば、自分の頭で納得できないことを受け入れない、宗教的な権威の前に思考停止しない、霊魂の存在
を信じないということです。信じる心を強くすることが信仰だとか、迷わない不動心を確立することが信心だとするような
考えは、明らかに誤りです。
を信じないということです。信じる心を強くすることが信仰だとか、迷わない不動心を確立することが信心だとするような
考えは、明らかに誤りです。
疑う心を否定したり、恥ずかしく思うことは誤りで、仏教を学ぶということは、この疑いの心を、徐々に徐々に、晴らし
て行くプロセスですから、頭から信じろ、みたいな話は、決して信じてはいけません。信じる気持ちは、自然に育つもの
ですから、あなたは信じないぞと思っていればいいのです。
て行くプロセスですから、頭から信じろ、みたいな話は、決して信じてはいけません。信じる気持ちは、自然に育つもの
ですから、あなたは信じないぞと思っていればいいのです。
「如来より賜りたる信心」と親鸞は言っています。本当の信仰心は(向こうから)自然にやってくるもので、自分の頭で
固めてつくるものではないからです。つくったものは壊れるのは道理ですし、なによりも、信じていないことは、実は、本
人が一番よく知っているのではありませんか。自分の頭でつくった信念など、どうして信じることができますか。わたし
は、「信じる」ということすら必要ないのではないか思っています。
固めてつくるものではないからです。つくったものは壊れるのは道理ですし、なによりも、信じていないことは、実は、本
人が一番よく知っているのではありませんか。自分の頭でつくった信念など、どうして信じることができますか。わたし
は、「信じる」ということすら必要ないのではないか思っています。
誤解しないでいただきたいのですが、濁川さんは、仏教の話をしているのです。
つまり、正しく「信じる」ためには「信じてはいけない」のです。
自らの「感性」と「知性」に背くことなく、「信じる」ことの出来る強さへの歩みを、急がずに一歩一歩進めたいものです。
文 ・ 星野 上
当サイトは、読書中心の内容であるために、どうしても頭でばかり考えることに陥ってしまうのを戒めることがいたるところで強調されていますが、
以下のページもそうした関連のものです。
以下のページもそうした関連のものです。
|
|

