新館 堀口藍園と渋川郷学

日本史を追っているとどうしても、天保、寛永、享保などといった和暦に悩まされます。
どうして西暦で統一できないのだろうかとはじめは思ったものですが、歴史を学んでいくうちに、その時代はそうした表
現が使われていたからというだけでなく、時代、世相を表現する方式として、徳川家光時代、吉宗時代などというよりも
はるかに、時代と不可分の表現としてゆるぎないものであることが次第にわかってくるものです。
現が使われていたからというだけでなく、時代、世相を表現する方式として、徳川家光時代、吉宗時代などというよりも
はるかに、時代と不可分の表現としてゆるぎないものであることが次第にわかってくるものです。
しかし、すべての和暦表現を頭に入れることなど歴史家でもない限りそうできるものでもないく、やっぱり、不合理この
うえないことを感ぜざるをえません。
うえないことを感ぜざるをえません。
そこで、記述上は必ず西暦をカッコなどで併記することが定着しているわけですが、日本史の魅力がそれぞれの時代
でたくさん見えてくればくるほど、誰しも歴史年表のお世話になることが人一倍増えてくるのは同じようです。
でたくさん見えてくればくるほど、誰しも歴史年表のお世話になることが人一倍増えてくるのは同じようです。
そして、年表を見たときにいつも、あれっ、こんな人が、こんな出来事が同時代のことだったのかとおどろかされるの
です。
です。
ときどきお客さんから、年表や事典を1冊まるごと一気に読んでいるはなしを聞きましたが、私には当初その感覚がと
ても理解できませんでした。
ても理解できませんでした。
ところが、歴史の知識が飛鳥・白鳳時代、戦国時代、明治維新、十五年戦争などの節目を軸に少しずつ増してくるに
したがい、年表を読むことの楽しさが私にも次第にわかるようになってきました。そんなときに、座右における年表を1
冊決めると、また加速的に歴史が面白くなってきます。
したがい、年表を読むことの楽しさが私にも次第にわかるようになってきました。そんなときに、座右における年表を1
冊決めると、また加速的に歴史が面白くなってきます。
【余談】 元号の表記については、前述したように、歴史を知るには不可欠の知識と認識していましたが、加藤周一が西暦を優先すべきとして
次のように喝破しています。
次のように喝破しています。
私は、「井原西鶴も、与謝蕪村も、日本を代表する文人で元号でいえば、西鶴は元禄、蕪村は天明に没している。それで、この二人の間に、ど
れくらいの時間的距離があるか、即座にいえますか?」と福田(恆存)さんに聞いたんですが、答えられなかった。そこで、「私なら言下に答えられ
ます。西鶴は17世紀の末、蕪村は18世紀末だから、およそ100年の間がある」といった。これは能力の差じゃなくて、元号を採用するか、西暦を採
用するかだけのちがいで、私が便利な方を使ったからです。それに、元号は、日本という集団内でしか通じないんで、国際関係をみていくときに
は、全く不便な道具です。(加藤周一・凡人会『「戦争と知識人」を読む』青木書店より)
れくらいの時間的距離があるか、即座にいえますか?」と福田(恆存)さんに聞いたんですが、答えられなかった。そこで、「私なら言下に答えられ
ます。西鶴は17世紀の末、蕪村は18世紀末だから、およそ100年の間がある」といった。これは能力の差じゃなくて、元号を採用するか、西暦を採
用するかだけのちがいで、私が便利な方を使ったからです。それに、元号は、日本という集団内でしか通じないんで、国際関係をみていくときに
は、全く不便な道具です。(加藤周一・凡人会『「戦争と知識人」を読む』青木書店より)
加藤周一は福田恆存と政治的立場の相違によってではなく、この議論をしてから疎遠になったという。
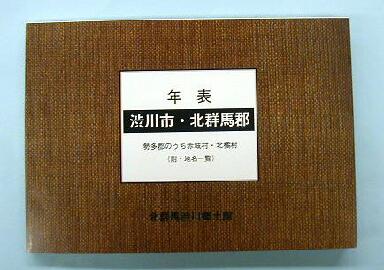
北群馬渋川郷土館の小山 宏さんと戸鹿野美和さんの編集による地元の郷土史年表。渋川市誌の年表などもありますが、日本史年表などと違
って、元になる年表がないだけに、歴史上の何を入れて何を削るか、大変な苦労をされてつくられたものだと思います。日本中にこうした地道な作
業をされる人が、各地に必ずといっていいほどおられるのは嬉しいばかりです。
って、元になる年表がないだけに、歴史上の何を入れて何を削るか、大変な苦労をされてつくられたものだと思います。日本中にこうした地道な作
業をされる人が、各地に必ずといっていいほどおられるのは嬉しいばかりです。
渋川・北群馬地方の群馬県民必携の1冊。
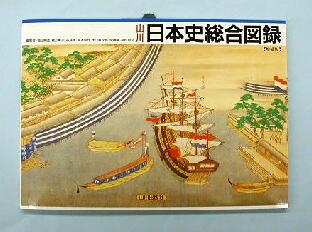
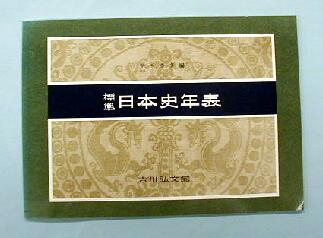
かつて、学習参考書のコーナーにしかおかれていなかったこうした年表が、どこかの本屋さんのアイデアで一般書のコーナーにもおかれるように
なり、時代劇ドラマ鑑賞の補助役などとして、不可欠の本になりました。
なり、時代劇ドラマ鑑賞の補助役などとして、不可欠の本になりました。
ところが、お客さんからよく聞かれるのは、もっともっと簡単な本を希望されている場合が多いようです。
B5四ツ折くらいのもので主要な年代が確認できるシンプルなものを多くの方がさがしています。中・高校生の年代暗記用の薄い新書版の本よりも
っとコンパクトなもののようで、こうした本は実用書の版元がどこか出版してくれれば、きっとロングセラーになると思います。
っとコンパクトなもののようで、こうした本は実用書の版元がどこか出版してくれれば、きっとロングセラーになると思います。
お客さんの意見をいろいろうかがって、既存の年表では何が不満なのかわかってきたので、正林堂版簡易年表(群馬・渋川を軸にしたもの)を思
いきって作ってしまおうと思っています。
いきって作ってしまおうと思っています。
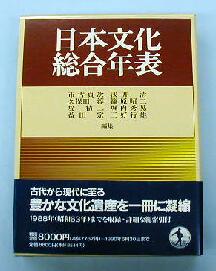
「文化総合年表」と題すると、結局、政治・社会から学問、宗教、美術、芸能、文学などほとんどなんでも記載する必要になり、おかげで最も頼り
になる年表がこうしたかたちで出来上がったのでしょう。文献資料の少ない古い時代ほど、歴史年代解釈も分かれていることがらも多いため、その
時代の最も信頼できる典拠に基づいた年表が求められる。そうした期待にこたえた1冊。
になる年表がこうしたかたちで出来上がったのでしょう。文献資料の少ない古い時代ほど、歴史年代解釈も分かれていることがらも多いため、その
時代の最も信頼できる典拠に基づいた年表が求められる。そうした期待にこたえた1冊。
ところが、何かどうしても確認する必要のある場合を除いて、これだけの情報があるとどうも開くのも億劫に感じてしまい、意外とマメに活用するこ
とは難しいものです。
とは難しいものです。
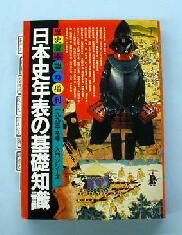
いろいろな年表を見ましたが、私はこの雑誌「歴史読本臨時増刊」を一番重宝しています。これは、様々な分野ごとの年表が載っており、珍しい
分野とその簡潔さで、古本の100円コーナーで見つけたものですが、手放せないものになっています。50種近くの年表が載っているのですが、事
件史年表、政治史年表、社会・経済史年表、近世漂流年表、航空史年表、仏教史年表、登山史年表などにはインデックスをつけて利用していま
す。
分野とその簡潔さで、古本の100円コーナーで見つけたものですが、手放せないものになっています。50種近くの年表が載っているのですが、事
件史年表、政治史年表、社会・経済史年表、近世漂流年表、航空史年表、仏教史年表、登山史年表などにはインデックスをつけて利用していま
す。
こうした分野別専門年表こそ、インターネットやデータベース機能の真骨頂を発揮できる分野なので、これから面白いサイトがたくさん出てくることと
思います。
思います。
参照リンク 年表・年譜一覧 http://www.ne.jp/asahi/coffee/house/TIMELINE/

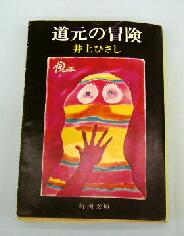
| |


次に紹介するのはただ時代の出来事を年代順にならべただけの「年表」というものが、どうしてこれほど深く個性的で
制作者の深い洞察を感じさせるものだろうかと、衝撃をうけた本。発売当時、この衝撃をお客さんに伝え、何人かのお
客さんにも感想を聞きましたが、皆同様の感想をもたれていました。
制作者の深い洞察を感じさせるものだろうかと、衝撃をうけた本。発売当時、この衝撃をお客さんに伝え、何人かのお
客さんにも感想を聞きましたが、皆同様の感想をもたれていました。
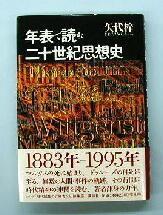

講談社から出たおかげで、発売時の普及度は高かったかもしれませんが、逆に大手出版社から出てしまうとどうしても寿命の短い商品になって
しまうのが難点。著者のタイプからも河出書房新社あたりが出してくれていれば、おそらくもう少し息長く入手できる本になったと思われるのに残
念。
しまうのが難点。著者のタイプからも河出書房新社あたりが出してくれていれば、おそらくもう少し息長く入手できる本になったと思われるのに残
念。
【訂正とお詫び】
上記のような叫びが届いてなのかどうか、講談社学術文庫から2006年4月に本書が刊行されました。
そうです。息長く良書を普及させるには講談社学術文庫!
ちくま学芸文庫とともに、もっとも信頼できるシリーズのラインナップに当然入れられるべき本です。
講談社様様が見落とすはずがありません。
講談社様!重ねて失礼をお詫び申し上げます。
もう少し付け加えるならば、歴史というものを事件や著名人物の羅列にとどまることなく、歴史の生命とか真理といっ
たものに触れた本というものはとても少ないものです。
たものに触れた本というものはとても少ないものです。
概説的な入門書や総合的な教科書の類はたくさん溢れているのに。
ここで二点だけ、歴史の流転のダイナミズム、人間の認識発展の歴史を生きいきとえがいた本を紹介させていただき
ます。
ます。
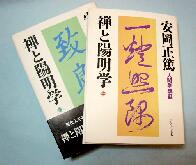
本書にはいくつもの紹介したいポイントがありますが、中国の宋から元へ、元から明の時代への変遷の叙述は、歴史とはこういうふうに語っても
らえれば誰もが理解できるというお手本を見せてくれます。
らえれば誰もが理解できるというお手本を見せてくれます。
陽明学の研究で有名な著者ですが、仏教、老荘思想、西洋哲学などなんでも縦横に駆使して
年表のあらわす一見客観的な年代数字の流れ(客観的な時間の流れというのはあるのだろうか?)を見ていると、現
代のめまぐるしい勢いで進歩しているかのような社会や技術進化のスピードが、はたしてほんとうにスピードアップした
姿なのかと、ふと疑問に思えてくることがあります。
代のめまぐるしい勢いで進歩しているかのような社会や技術進化のスピードが、はたしてほんとうにスピードアップした
姿なのかと、ふと疑問に思えてくることがあります。
たとえば、仏教に代表される日本思想史をみると、
「聖徳太子から空海までまさに二百年、空海から鎌倉まで四百年、鎌倉から今日まで八百年。いったい、二百年、四百
年、八百年というのは何を意味するのあろうか。」
年、八百年というのは何を意味するのあろうか。」
玉城康四郎『仏教の根底にあるもの』講談社学術文庫
といったように、逆に進歩のスピードが遅くなってきているかのような姿もあります。
また、激動の時代、混迷の時代など様々な言われ方をしている時期を比較してみても、結局、時代の変化は、一貫し
てその時々の世代サイクルでしかおきていないのではないか、とも思えてきます。
てその時々の世代サイクルでしかおきていないのではないか、とも思えてきます。
つまり、近代、現代史でみても、20年、40年のサイクルで歴史が転換しているように、戦国の世、さらには奈良時代
まで遡っても、社会のパラダイム転換は20年、40年といったスパンで動いていることに変わりがないようにも見えま
す。
まで遡っても、社会のパラダイム転換は20年、40年といったスパンで動いていることに変わりがないようにも見えま
す。
日清・日露戦争から、太平洋戦争の終わりまで約半世紀、敗戦からバブルの崩壊までの半世紀、それぞれ激動の時
代と言われていながらも、それぞれの大きな流れの方向を見てみればそれほど変わっているわけでもない。
代と言われていながらも、それぞれの大きな流れの方向を見てみればそれほど変わっているわけでもない。
その意味でバブル後の「失われた十年」などという言われかたがされますが、半世紀後の社会がどのような方向にあ
るのか見据えておかないと、あれよあれよいう間に時代の流れのままに無為に20年、30年が過ぎ去ってしまう恐れが
あります。
るのか見据えておかないと、あれよあれよいう間に時代の流れのままに無為に20年、30年が過ぎ去ってしまう恐れが
あります。
ところが、その時代、その時代を代表する世代が力を発揮するのは、10年、20年といったサイクルであることも変わ
りはないのでしょうが、ここに、これまでの社会には無かったまた新しい要素がでてきています。
りはないのでしょうが、ここに、これまでの社会には無かったまた新しい要素がでてきています。
それは平均寿命が飛躍的に伸びてきたことです。
「孝行したいときには親はなく」という言葉がありますが、これは60歳にもなれば多くの親は亡くなっていた時代のは
なしです。
なしです。
今では、ややもすると子供が定年退職したときでも、まだ親は家業などで現役で働いていたりすることが例外ではなく
なってきています。
なってきています。
「孝行したいときに、親はまだまだいるから安心して孝行なさい」という時代。
常に、若い世代が、新しい時代の息吹を生むことに変わりはないにしても、一旦現役を退いたかの世代が昔とくらべ
てあまりにも多くいるので、そう黙っているわけにもいかなくなってきました。
てあまりにも多くいるので、そう黙っているわけにもいかなくなってきました。
人生短いようで、結構長くなってきていることは確かなだけに、もっと10年後、20年後、さらには50年後を見据えた
ものの見かたを習慣づけないといけないのではないでしょうか。
ものの見かたを習慣づけないといけないのではないでしょうか。
歴史年表を眺めていて、ふとこんなことを感じました。
さらに追記
時の流れに関してもうひとつ、面白い話がありました。
日下公人が言っていたことですが、今の世界の人口は5、60億人といったところ。
ところが、これだけの人数に世界人口が膨れ上がったのはつい最近のこと。
よく昔からお盆の時期になると、いまは、これまで死んだすべての人々が歩いてかえってくるからものすごい混雑にな
っているのだろうなどと話していたものですが、ある統計によると、
っているのだろうなどと話していたものですが、ある統計によると、
「これまでの人類が地球上に現れてから今日までのすべての人間を合計すると、実は百億人にも満たないのだそうで
す。キリスト教は、人間の魂は神様が創ったと言っていますが、その神様の創った魂の半分以上は今、この地上に生
きて、歩いているということらしい。」
す。キリスト教は、人間の魂は神様が創ったと言っていますが、その神様の創った魂の半分以上は今、この地上に生
きて、歩いているということらしい。」
過去の長い歴史の積み重ねの重みも大きいかもしれないが、現代の今いる人々のこの瞬間の選択の力もずっと大き
いのではないか、と。
いのではないか、と。
文 ・ 星野 上
| |
|
|

