第三テーマ館 日航123便御巣鷹山墜落事故

日航機の墜落事故で一躍知れ渡った「御巣鷹山」ですが、実際に事故のあった山はそのような名前が正式名の山で
はないので、後に、上野村黒沢村長などの提唱により、「御巣鷹の尾根」と命名されたものです。
はないので、後に、上野村黒沢村長などの提唱により、「御巣鷹の尾根」と命名されたものです。
御巣鷹山と呼ばれる山は、「群馬県の多野郡だけでも36ヶ所、その他に13ケ村の山野に全県的存在し、特にタカ狩が
幕末の衰退期に向う下限まで、巣鷹の供給の役割を果たしていたことが分かる」 小山宏 「御巣鷹概論」『渋川市有馬
郷土館八周年記念 泉花譜』渋川有馬郷土館 刊 より
幕末の衰退期に向う下限まで、巣鷹の供給の役割を果たしていたことが分かる」 小山宏 「御巣鷹概論」『渋川市有馬
郷土館八周年記念 泉花譜』渋川有馬郷土館 刊 より
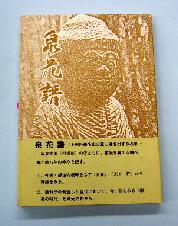
日頃おつきあいのある、北群馬渋川郷土館の小山さんの出された本ですが、こんなに大事な論文が入っていること
を知りませんでした。
を知りませんでした。
本書はある古書展でみつけてきたのですが、『泉花譜』なんていう背のタイトルをみただけでは、およそこんな論文が
載っているなんて想像はつかないものです。運良く渋川市の文字が目にはいったために、なかをパラパラめくって気が
つくことができました。
載っているなんて想像はつかないものです。運良く渋川市の文字が目にはいったために、なかをパラパラめくって気が
つくことができました。
資料も含めて三十数ページほどの論文なのですが、以下に、目次を転載します。
御巣鷹概論 ―上州御巣鷹山を中心として―
一、はしがき
二、「御鷹」に用いられるタカの種類と、上州における生息状況
1、御鷹の種類
2、生息が確認されているワシタカ目
三、上州の御巣鷹山(一)
1、上州の御巣鷹山一覧
四、上州の御巣鷹山(二)
1、巣山の制
2、江戸幕府中期以降の鷹出所名録
3、幕末の事情
4、「鷹立」と「お竹やぶ」地名の考察
五、御巣鷹山既刊文献について
1、『群馬県史研究』2、「御巣鷹山研究序説」、『群馬県史』等に対する私見
2、渋川市指定重要文化財「旧入沢家住宅及び所蔵文書」について
3、黒沢家文書の内容
4、絵画、古文書等にみられるタカ狩
六、御犬と御鷹犬
1、御鷹部屋と御犬部屋
七、資料解題
八、御鷹関係古文書目録(上野国・群馬県)家別・抽出
鷹狩は徳川幕府の崩壊によって大きく消失し、第二次大戦によって皇室に皇室に伝統的に継承されてきたものも姿
を消し、明治天皇によって一時復活したものも絶え、最後に東北地方の民間猟師に残された鷹狩も昭和三十年代をピ
ークとしてとぎれ、その後、愛好者間で趣味的に残存したものでさえ新しい狩猟法の改訂や、条約などの制約から廃絶
の方向に向っているといえる。 (同書 65ページ)
を消し、明治天皇によって一時復活したものも絶え、最後に東北地方の民間猟師に残された鷹狩も昭和三十年代をピ
ークとしてとぎれ、その後、愛好者間で趣味的に残存したものでさえ新しい狩猟法の改訂や、条約などの制約から廃絶
の方向に向っているといえる。 (同書 65ページ)
二、「御鷹」に用いられるタカの種類と、上州における生息状況 には興味深い以下のような記述があります。
タカ類の生態と地理的条件からみると、例えば渋川市が榛名山系の谷口集落に発達した近世の農村社会の構造か
ら、タカ類繁殖の格好の条件を具備している状況がわかる。
ら、タカ類繁殖の格好の条件を具備している状況がわかる。
タカ類などのいわゆる猛禽類は、他の鳥獣の生息状況の頂点にあって、タカ類の繁殖と生息する条件があることは、
傘下の多様な生物を生息させる好適な自然条件を保っている地域といえる。
傘下の多様な生物を生息させる好適な自然条件を保っている地域といえる。
この状況は拙稿『榛名山東麓の野鳥』「郷土渋川」(昭和60)に記したが、最近新たにタカ類の生息を確認しており、
およそ四十年間の観察記録から、地名の鷹立(字名)を含んだ地域におけるタカの繁殖が永続してきたことは、ほぼ間
違いないことと考えられる。(榛名山、二ツ嶽の噴火や浅間の爆発で一時、離散したタカ類が戻って生息を続けたらし
い。)
およそ四十年間の観察記録から、地名の鷹立(字名)を含んだ地域におけるタカの繁殖が永続してきたことは、ほぼ間
違いないことと考えられる。(榛名山、二ツ嶽の噴火や浅間の爆発で一時、離散したタカ類が戻って生息を続けたらし
い。)
一般に巣鷹を産するのは深山幽谷が想定されているが、自然条件からみると、集落近辺に突き出した山で、谷の構
造を地理的にもつ地域が圧倒的に多く、タカ類の営巣地となる条件を備えている。
造を地理的にもつ地域が圧倒的に多く、タカ類の営巣地となる条件を備えている。
その条件のうち、タカの餌となる植物食性の鳥類は田畑や山付の境界に最も多棲していること、つまり、タカの餌が
豊富であること、巣山への出入に、谷間の上昇気流を上手に利用していることが分かる。
豊富であること、巣山への出入に、谷間の上昇気流を上手に利用していることが分かる。
六章の御犬と御鷹犬では、巣鷹が江戸まで搬送される過程とその厳重な体制なるがゆえの困難が以下のように述
べられています。
べられています。
上州産の巣鷹の継送先が何処であったかということは、上州に限らず御鷹と民衆とのかかわりを考察する上で大事
な要素で、巣下しされたヒナの先触、逓送は警護、夫役、接待において生物であり大切なものであり、死亡しやすいも
の、さらに別件であるが御鷹の餌となる活餌の継送にしろ、村役人は不寝番で苦労させられ、幕府御用を後立とした
御鷹関係の役人の専横に、どの村役人も難渋し、これが、発展して幕府自体が対策を講ぜざるを得ない状況にも立ち
至った。
な要素で、巣下しされたヒナの先触、逓送は警護、夫役、接待において生物であり大切なものであり、死亡しやすいも
の、さらに別件であるが御鷹の餌となる活餌の継送にしろ、村役人は不寝番で苦労させられ、幕府御用を後立とした
御鷹関係の役人の専横に、どの村役人も難渋し、これが、発展して幕府自体が対策を講ぜざるを得ない状況にも立ち
至った。
鷹場の職制も『諸家譜』によると、近世初頭では、鷹匠頭・鷹師頭・鷹匠・手鷹匠・手鷹師・鷹師・鷹役・手鷹役・鷹方・
巣鷹役・鷹時飼・鳥屋飼・鷹匠同心・雛頭・犬牽頭・犬飼・餌指頭・餌指・鳥見役・鷹場奉行・網奉行・殺生奉行など、じ
つにさまざまな職制がみられる。
巣鷹役・鷹時飼・鳥屋飼・鷹匠同心・雛頭・犬牽頭・犬飼・餌指頭・餌指・鳥見役・鷹場奉行・網奉行・殺生奉行など、じ
つにさまざまな職制がみられる。
そもそも鷹場というものが国家にとってどのようなものであったのか、ということについては、根崎光男「江戸幕府鷹
場制度の成立過程」『幕藩制社会の展開と関東』吉川弘文館(1986/12)という論文を見つけました。
場制度の成立過程」『幕藩制社会の展開と関東』吉川弘文館(1986/12)という論文を見つけました。
「近年、鷹をめぐる歴史的諸関係がいくつか論じられているなかで、狩猟の一手段である鷹狩が律令制国家において
は天皇の権力と密接な関係をもち、また中世国家においても鷹にかかわる諸関係が整備されており、さらに中世から
近世への移行期論のなかでは鷹と守護公権とのかかわりなどが指摘されつつある。すなわち、歴史的経緯のなかで鷹
は権力ないし国家のあり方・しくみに直接関与し、権力の象徴としての側面をもつようになったというのである。
は天皇の権力と密接な関係をもち、また中世国家においても鷹にかかわる諸関係が整備されており、さらに中世から
近世への移行期論のなかでは鷹と守護公権とのかかわりなどが指摘されつつある。すなわち、歴史的経緯のなかで鷹
は権力ないし国家のあり方・しくみに直接関与し、権力の象徴としての側面をもつようになったというのである。
このように、鷹が身分制社会において権力の象徴であり、同様に鷹場がその象徴を具体的に誇示する場であるとす
れば、豊臣氏や徳川氏が統一政権を掌握維持していく過程で鷹場制度の整備に着手していくのは、支配の貫徹をは
かる政治権力の必然的要請であるとみてよいでえあろう。」とし、30ページほどの論文をまとめています。
れば、豊臣氏や徳川氏が統一政権を掌握維持していく過程で鷹場制度の整備に着手していくのは、支配の貫徹をは
かる政治権力の必然的要請であるとみてよいでえあろう。」とし、30ページほどの論文をまとめています。
| |
| |
|
|

