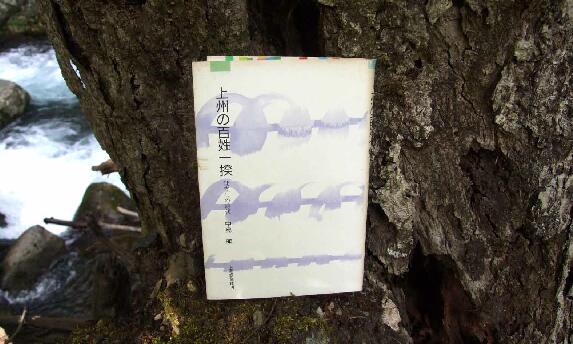
えてしてこの手の本は、一通りの資料を調査、整理しただけのものに終わってしまっている場合が多いのですが、本書は著者のしっかりした視
点に貫かれてまとめられたとても好感のもてる本です。
点に貫かれてまとめられたとても好感のもてる本です。
それは、上州の一揆のなかでも主に江戸時代後半(天明3年から慶応4年)に限定し、それを第三期「世直しの時代」と定義してその時代を中心
に述べられていることです。
に述べられていることです。
第一期は茂左衛門に代表される「代表訴訟型一揆の時代」と名づけ、近世上州の始まりから享保・寛延期頃(1735〜1750)を目安としている。
第二期は宝暦前後(1751)から天明初期(1783)までとし、これを「広域型(広域闘争)一揆の時代と命名している。
第二期は宝暦前後(1751)から天明初期(1783)までとし、これを「広域型(広域闘争)一揆の時代と命名している。
本書で紹介されている一揆で、興味深かったのは根利村でおきた「ねだり食い」戦法と押し売りならぬ「押し借り金」戦法の紹介です。天保七年
に、利根郡根利村(利根村)で村内の農民全員を集め「金子押し借り」要求の行動を呼びかけた際、この闘争に不参加の者がいたならば、食糧不
足下のため、その者の家に押しかけ食事を強要することを取り決め、実際に勇八ひとりが参加しなかったため、その家に押しかけたという。
に、利根郡根利村(利根村)で村内の農民全員を集め「金子押し借り」要求の行動を呼びかけた際、この闘争に不参加の者がいたならば、食糧不
足下のため、その者の家に押しかけ食事を強要することを取り決め、実際に勇八ひとりが参加しなかったため、その家に押しかけたという。
本書で様々な一揆の実態を教えられるのですが、江戸時代後期の一揆ともなると、赤貧の貧しさゆえばかりでなく、農民がいかに高度な政治的
要求と組織的な闘いを行なっていたかがわかります。
要求と組織的な闘いを行なっていたかがわかります。
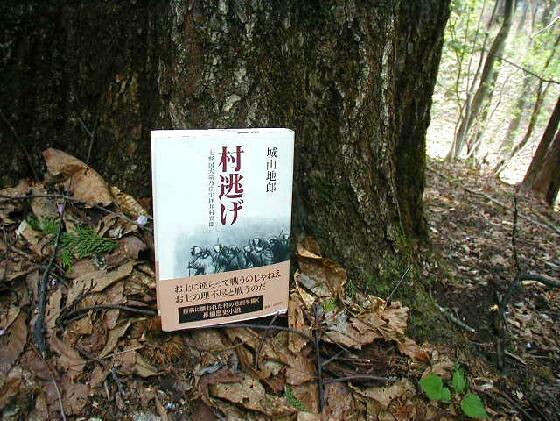
ここでの「村逃げ」とは、逃散の一形態(逃げるだけでない組織的移民)とも思えるが、疫病にとりつかれた村が生き残りをはかるために、自ら疫
病にかかった家族と村を焼き払い、赤城山奥深くの山地に逃げ隠れ、新しい村を築こうと努力をする。火付けだけでも重罪であるのに、家族を捨
て、村逃げをはかったものが、許されるはずがない。
病にかかった家族と村を焼き払い、赤城山奥深くの山地に逃げ隠れ、新しい村を築こうと努力をする。火付けだけでも重罪であるのに、家族を捨
て、村逃げをはかったものが、許されるはずがない。
「捕まれば、大人だけでねえ、子供まで打首になる。だからといって、あのまま村に居残っていれば、村中の者が疫病になるのを待つことにな
る。俺あ達が村逃げをしてきたのは、生きたいがためだ。どんな事があっても、俺あ達は生きて宇坪井村を造らなければならねえ。」
る。俺あ達が村逃げをしてきたのは、生きたいがためだ。どんな事があっても、俺あ達は生きて宇坪井村を造らなければならねえ。」
しかし、当然、お上の追及は逃れえず、悲しい結末は避けられないが、生き残ったものが、村をつくるために力をあわせて新しい家族の絆をきず
こうと努力しあう。
こうと努力しあう。
本書は、当初著者が自分の町に伝わる伝承を論文としてまとめ上げたところ、研究者から史実として断定できない内容のものでも文章として普
及すると、いつのまにかそれが史実であるかのように定着してしまうとの指摘をうけため、改めて小説としてまとめあげたものだそうです。そうした
背景があるだけに自費出版にしては、完成度のとても高い作品になっています。
及すると、いつのまにかそれが史実であるかのように定着してしまうとの指摘をうけため、改めて小説としてまとめあげたものだそうです。そうした
背景があるだけに自費出版にしては、完成度のとても高い作品になっています。
(まだ、著者個人で本書の在庫はお持ちのようです)
参照ページ 『村逃げ』著者からのお手紙
「村逃げ」「逃散」「走り」などの農民の行動は、必ずしも逃げるばかりの逃亡行動ではなく、農民の持つ最後の権利行
使の側面ももっていたようです。
使の側面ももっていたようです。
多くの「村逃げ」「逃散」「走り」の場合、ただあてもなく領地から逃げ出すのではなく、受け入れてもらえる近隣の場所
の目星をつけてから移動しています。
の目星をつけてから移動しています。
受け入れ側からすれば、新たな農地開墾などの労働力が流入してくる利点につながり、村が家を建てる協力をした
り、領主からも様々な優遇処置をうけたりする。
り、領主からも様々な優遇処置をうけたりする。
逃げ出された領主の側も、耕作人口の流出は直接生産力の低下につながるため、様々な出戻り優遇処置もおこなっ
ています。
ています。
さらに近隣の領主同士が、農民の返還のための涙ぐましいばかりの交渉を重ねている例もあることを下記の本で知
りました。
りました。
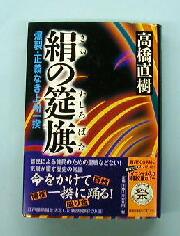
[要旨]
江戸爛熟の田沼時代。絹市場の置かれた上州藤岡の町は、江戸豪商の買付け先として、急速な発展を遂げた。好景気に浮かれる藤岡に、突
如、幕府より絹糸改会所設置の命令が下る。財政難に苦しむ幕府の、運上金取り立ての一環と見えた改会所。しかしその裏には、絹市場を独占
する絹宿衆と、その利権を狙う在郷商人との対立の構図が。金と欲の絹宿・新井喜兵衛は、改会所を撤廃に追いこむべく、危険な賭けに出る。一
揆だ。領主不在の西上州、幕府政治の矛盾に隠された無法地帯に、煽動された農民は蜂起する。しかし一揆を指導する者たちの心はひとつにあ
らず。博徒名主、アジテーターの修験者、剛力の百姓、みな別々のゴールをめざし、数万に膨れあがった一揆勢とともに絹街道を驀進していった
…。注目の気鋭が従来の「百姓一揆」観を覆す、新感覚時代小説。
如、幕府より絹糸改会所設置の命令が下る。財政難に苦しむ幕府の、運上金取り立ての一環と見えた改会所。しかしその裏には、絹市場を独占
する絹宿衆と、その利権を狙う在郷商人との対立の構図が。金と欲の絹宿・新井喜兵衛は、改会所を撤廃に追いこむべく、危険な賭けに出る。一
揆だ。領主不在の西上州、幕府政治の矛盾に隠された無法地帯に、煽動された農民は蜂起する。しかし一揆を指導する者たちの心はひとつにあ
らず。博徒名主、アジテーターの修験者、剛力の百姓、みな別々のゴールをめざし、数万に膨れあがった一揆勢とともに絹街道を驀進していった
…。注目の気鋭が従来の「百姓一揆」観を覆す、新感覚時代小説。
| |
|
|

