
| (本書 25ページより)
|
そんなことを言っても、家のローン、子供の養育費などをかかえていながら、この就職難の時代に簡単に転職などできるものかとの
言葉が返ってくるのもよくわかります。
しかし、もう一度、この本を読んでゆっくりと考えてみてください。
「楽しい仕事」にめぐりあえるかどうかは、容易いことではないかも知れませんが、今、携わっている仕事が「楽しくない」ということは、
その人自身にとっても、会社にとっても、また家族にとっても、決して良いことではありません。
どの本かは思い出せませんが、本書と似たような本の帯に書いてあった言葉ですが、「仕事がつまらない」ということは(どんなに豊
かな趣味を持っていようが、楽しい休日をすごそうが)「一年のうちの300日近く、つまらない日々を過ごしている」ことになるのです。
そもそも仕事とは「楽しいものではない」、我慢や苦労の代償としてはじめて報酬があるのだという人も多いことでしょう。
でも、仕事で成果をあげる、売上げを伸ばす、とはいったいどのようなことでしょうか。
それは、「我慢」や「苦労」の代償としての報酬を望んでいる限り、いくら「苦労」や「我慢」を重ねても決して大きな報酬は巡って
くるものではありません。
そのような考えの従業員がたくさんいては、会社も決して業績を伸ばすことはできません。
報酬というものは、「我慢」や「苦労」の先に、それによって「喜んでくれる」顧客や従業員が見えてこそ、はじめて得られるものだからです。
そして、「仕事が楽しくない」という状態の最も大きな損害は、その人やその人のいる会社から「創造性」そのものを奪ってしまうことです。
繰り返すまでもなく、この時代、安易に転職を考えるなどということはできるものではありません。しかし、ここで必要なのは、なにも
転職することとは限りません。
今、または将来の仕事が面白く、楽しくなることさえできれば良いのです。
最大の「創造性の源泉」さえ、手に入れられればよいのです。
それでも現実はなかなか、という方に、他のページでも紹介した言葉を再記します。
現実にはなかなか変えることは難しいといいますが、
「いったいあなたは誰に頼まれて生きているのですか?
あなたの頭のてっぺんから足のつま先まで、どこか人から借りてきている部分でもあるのですか?
あなたのこころのどこかに、他人から借りている部分でもあるのですか?
あなたがどうするか、それはあなた自身が全権持っていることではないのですか?
わからなければ人に聞く、調べてみる。力が足りなければ応援を呼ぶ。
人は誰しもオギャーと生まれたときから生きていくに必要なものはすべて持って生まれてきているといいます。
たとえ自らは何もできない赤ん坊でさえ、周りのひとが放っておけないような愛くるしい可愛さを身につけているものです。
とはいっても、まだなかなか変えられない人も私を含めて多いことでしょう。
でも、少なくとも、他人のせいにしないことだけは心がけておきましょう。
掟破りですが、中谷彰宏流に、本書タイトルのエッセンスをちょっと抜き出してみましょう。
(成功者は)みんな、人生のある時点で
仕事に対する目標を変えた人たちだ。
今日の目標は明日のマンネリ。
「僕がいままでに掲げた目標が一つだけある。聞きたいかね?」
ぜひ、と私は答える。
“明日は今日と違う自分になる”だよ。
きみは、最初に陸にあがった魚は
長期にわたる目標を持っていたと思うかね?
これは僕の大好きな言葉の一つなんだ。
“遊び感覚でいろいろやって、成り行きを見守る”
必要は発明の父かもしれない。
だけど、偶然は発明の父なんだ。
何を試してきたのかね。
目標に関するきみの問題は
世の中は、きみの目標が達成されるまで、
じーっと待っていたりしないということだよ。
成功するというのはね、右に倣えをしないっていうことなんだ。
成功の宝くじでは、勝つチャンスは何百と手に入るし、
そのほとんどは大損するようなものじゃないってことを。
適切な時とか完璧な機会なんてものはないということ。
君たちの事業は、
試してみた結果、失敗に終わったんじゃない。
試すこと自体が欠落していたんだ。
人は、変化は大嫌いだが、試してみることは大好きなんだ。

この続編は、組織や人間関係について語っていますが、どうせ自分には難しいあれに気をつかって、これに注意してなどということがたくさん書
かれているのかと思ったら、自分と共に闘える同僚や上司、部下に回り逢えるのはそう簡単なことではない旨が書いてあり、なるほど、よしっと思
い一気に読めました。
かれているのかと思ったら、自分と共に闘える同僚や上司、部下に回り逢えるのはそう簡単なことではない旨が書いてあり、なるほど、よしっと思
い一気に読めました。

近代資本主義の問題に限らず、古く東洋思想でも「楽しむ」ということが、いかに重要であるか多くの人が語っています。
『論語』に「之を知るものは之を好むものに如かず。之を好むものは之を楽しむものに如かず」という語がありますが、確かに
名言であります。科学的考察から言っても、ぴったり当たっております。
知るという働きは、大脳の新しい皮質が司るものでありますが、然しこれを好むとか楽しむとかいう事になると、間脳や本具の
皮質と一致しなければ成り立たない。好むというのはより多く本能的でありますが、楽しむとなるとこれは後天的というか、理知
的なものが加わって来る。
「仁者は山を愛し、知者は水を楽しむ」という語にしてもそうであります。わざわざ愛すると楽しむを分けている。愛するのは
本能的な働き、それに理知が加わって楽しむということになる。そこで知者は楽しむのであります。
「仁者は山を愛す」とはより多く本能的な働きでありますから、どうしても愛するのであります。一方は愛すと言ったから、片方は
楽しむにした、というようなものでは決してないのであります。古人の的確な観察がはっきり証明されておるのであります。
そういう意味で面白いのが楽しむということであります。学問でも修養でも、これを楽しむという段階に入らなければ、本当では
ない。道楽という語がありますが、道が楽しいようにならなくてはいけない。これは楽道でも宜しいのでありますが、道を楽しむ
までは、まだそこに、道と人とのあ相田に相対的な立場がある。渾然と一致してはじめて道楽になる。
佐藤一斎『言志四録』について

| |












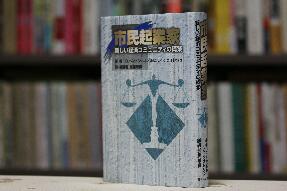




| 自分の想いに、実現のチャンスをあげたい。 でも、第一歩はどうすればいいんだろう? ・・・そんな想いを胸に秘める方を応援する講座が全国各地で開催中です! この講座では、「社会起業」と呼ばれる動きの背景、 なぜ、「ひとり」が出会った問題や、ふだん感じていることが大切なのか、 といった、『動き出すための基礎知識』から始まり、 実際に、「どうやって、自分のアイデアを事業に立ち上げていくのか?」 という『アクションへの準備』を、みなさんと一緒に行います。 NPO法人ETIC.で、2002年からスタートした本ワークショップは、 これまで、全国各地で20回以上開催れ、若手起業家や学生だけでなく、 行政職員、主婦など、のべ500人以上が参加し、大好評を得ています。 今度はあなたの想いの出番です! |


「原発の設計に携わっていたとき・・・・・少なくとも私は・・・・・原発の建設というものが地域社会にどのような
インパクトを与えるのか、一度も考えたことはなかった。
原発が地域の様相を、あるいは個人の暮らしを一変させることに思いを馳せたことは一度もなかった。
・・・・・それはせいぜいい、原発を支えている“高度な技術”を一般の人びとが理解できないからだろう、
という程度のものだった。
・・・・・・多くの原発技術者の心の状態は当時もいまも、そのようなものであると思っている。
組織のダイナミックスは人の心をある特有の状態に仕向ける。批判的な精神は意識下に降り、価値判断
は停止し、組織の目的――原発をつくるということ――に向けて自己超越してしまう。
そのような状態にあっては、自分がいま何をなしているかを、社会というより大きなコンテキストに据えて
考えることはしないし、またできない。それは心理学でいうところの一種のj防衛機制であるのだろうが、
組織というのはいつでも個人の心理状態にそのようなマジックをかけるものだ。
たまたま属した企業が原発の企業だった、あるいは電力会社だった、というだけで、人はその日から熱心
な「原発推進者」に変わる。」
田中三彦 『原発はなぜ危険か――元設計技師の証言』 (岩波新書)より
ある子どもが父親に「お父さんは朝出れば夜中まで帰ってこない。話と言えば、怒鳴るか説教するだけ
じゃないか。そんなお父さんなんかいないほうがいい。」
その父親は遅くまで頑張って家族のために働いていると信じていたから、子どものその言葉にがくぜんとし、
ショックだったけれども、返す言葉が「なかったという。
(暉峻 淑子 『社会人の生き方』 119ページ)

| |
|
|

